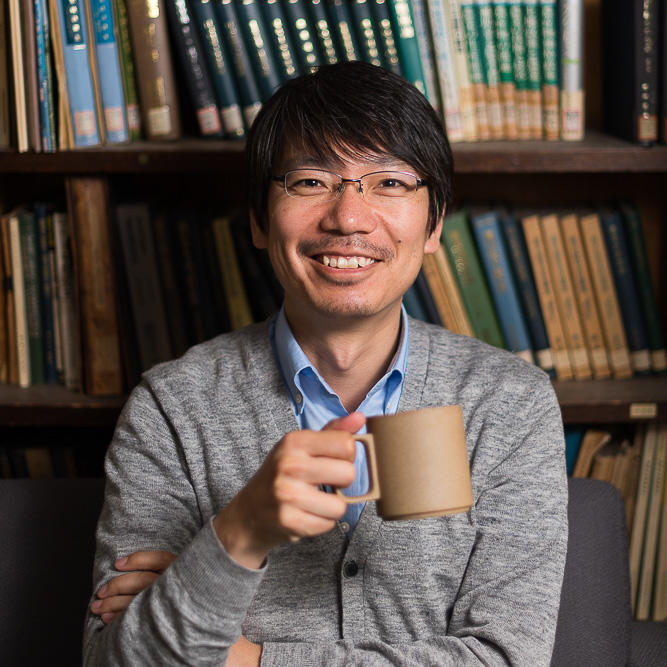いつかイギリスの歴史を振り返った時2020年はどのように記憶されているのだろうか。2020年は2016年から続いたEU離脱(Brexit ブリグジット)の混乱がついに決着し、政治的独自性を取り戻した記念すべき年になるはずだったが、イギリスはいまコロナ危機が大きな影を落としている。不確実な時代に踏み出したイギリスは、これからどこに向かうのか。農業の問題に限って直面している課題について考えてみよう。
public money for public goods
公共のお金は公共のために

EUの共通農業政策(CAP)の下にあったイギリスはBrexitによって独自の農業政策を決める「権利」を取り戻した。ポストCAPの農業政策が、2020年の2月にイギリス下院に提出されて政策の枠組みがほぼ決まった。その理念をあらわすキーワードが"public money for public goods"である。税金は農業経営そのものへの支援ではなく、農業が提供する(するであろう)公共的利益に使うというこの考えは、Brexit前から提案されてきたが、EUから離脱してイギリス独自の農業政策を実施できる政策的環境を手に入れたなかで、晴れて政策理念の核として登場した。
イギリスはEUのなかでも産業としての競争力を持った農業を目指しているという点で特徴的であるが、実際はEUからの「直接支払い」に農業所得の大きな割合を依存している。一経営あたりに支給される金額に上限はあるが、基本的には面積が多い経営ほど多くの支払いを受け取ることができる仕組みである。全ての経営形態の平均値では利益の61%が直接支払いによるものであり、仮に直接支払いがない場合42%の経営体が赤字になるという。(注1)
それを7年間かけて徐々に後退させながら、public money for public goodsへと移行する。直接支払いは、貰っている金額に応じて段階的に削減されていく。(注2)
注1)National Audit Office "Early review of the new farming programme"2019,Juneより。2014-2015、2016-2017年の実績値を元にしている。
注2)Farmers Weekly記事 "what the new agricultural bill contains for farmers"より。直接支払いの削減は、イングランドだけが適用され、北アイルランド、ウェールズ、スコットランドでは直接支払いは継続されることになっている。
農業界における"public goods"としての環境保全

政策理念の転換は、環境保全の団体や持続的な農業、食料生産を目指す団体から歓迎された。化学肥料や農薬の使用量を削減し、土壌を健康に保つ、花粉を媒介する昆虫や自然環境を豊かにする、森林のメンテナンスをする、植林をする。こうすることで水の確保、洪水の防止、野生の動植物の保全に役立てる。もちろん、農業自体もより持続的なやり方に転換することがもとめられる。EUの共通農業政策でも環境保全への助成はされてきたが、その効果については環境保全の団体などからは実効性が疑問視されてきたのである。
こうした流れに対して、農業者の団体、特に大規模でいわゆる企業的な農業者を主なメンバーとするイギリス最大の農業者組織National Farmers Union(NFU)は、反対するのかと思いきや、むしろ積極的な姿勢を見せている。「その方向にむけて、私たちも取り組みます。そのためにも政府と一緒に頑張りましょう」という現実的・実利的なスタンスを打ち出し「Net-Zero-Farming」という目標を掲げた。

農業分野に向けられている視線のなかでも大きなものに「温室効果ガス」の問題がある。農業からの排出量はイギリス全体の10%をしめている。土壌からの排出、農業機械に使用する化石燃料、さらに反芻動物家畜由来のガス。NFUはそうした問題に真剣に取り組み、2040年までに農業全体として温室効果ガスの排出と吸収・固定をイコールゼロとするような農業のあり方を目指すことになった(イングランド及びウェールズが対象)。適切な輪作や土作りという農業の基本的技術の実施にはじまり、不(省)耕起による土壌へ炭素固定、GPSを導入した精密農業による施肥料の厳密な管理など、「有機農業VS慣行農業」という単純なものではなく、可能なあらゆる技術を全方位的に適用することで持続的な農業を実現しようというものだ(注3)。これはイギリス全体として2050年までに温室効果ガスの排出量の実質0をめざす目標に沿った形で、それを10年も前倒しで目指すというとても大きな挑戦である。
public money for public goodsの流れは、いまは農業者としても当然のものとして受け止めている(様に見える)、むしろそうせざるを得ないのがイギリスにおける農業の立場なのだ。
public money for public goodsを具体的に実現するには課題も指摘されている。
①農業に関連して、支援すべきpublic goodsとは何か
②対象となるpublic goodsに対してどのように支援をするのか
③その支援水準はどう設定するのか(注4)。
さらにいえば、政策実施のモニタリング、実効性の評価(効果が発現するまでには中長期にわたるだろう)という問題も考えられる。
注3)NFU "Achieving Net Zero Farming 2040 Goals"
注4)Ian J. Bateman, Ben Balmford "Public funding for public goods: A post-Brexit perspective on principles for agricultural policy" Land Use Policy, 79, 2018, 293-300
ポストコロナのイギリス農業政策
そして「エシカル」が示す射程とは
いずれにしても、イギリスにおける農業の立場・役割・方向が明確化されたその矢先にコロナ危機が押し寄せたのである。いまイギリス国内ですぐに食料不足の問題が起きているわけではない。だが、野菜の収穫を担ってきた東欧からの労働者、オランダのロッテルダム港やドーバー海峡を結ぶ物流インフラ。イギリス国民の食を支えてきたこうした「当然の条件」が、当たり前ではなく不確実だということを痛感させられている。そのなかで、今後のイギリス農業はどのような理念のもとに展開していくのだろうか。
国民への食料の安定的な確保を実現する、という方向がより強調されていくことになるかもしれない。実は、今回の農業政策を決める過程でのパブリックコメントとしても食料自給の重要性を政策にも盛り込むようにという意見があり、それが政策に反映されてはいた。かつて食料自給率を向上させて日本の見本とも言われたイギリスも一時期80%近くあった自給率は52%程度にまで落ち込んでいた(注5)。

新しい農業政策ではpublic money for public goodsの理念が前面に出されてきたのだが、コロナ危機をきっかけにその流れも変わるかもしれない。そして食料の自給を具体的にどのような目標として定め、どのように実現するのかという課題により真剣に向き合わなければならなくなるだろう。
この課題はブリテン諸島という土地において、これからの気候変動も考えながら、何を作り、何を食べていくのか、という土地利用のあり方と結びつく。それはこれから何を食べていくのかという国民の食の課題でもある。イギリスでは、食品の安全性や動物福祉、環境への影響といった点が、食品の輸入を議論する時に最も重要な論点であった。いまはそれにくわえてそもそも外国に食料を依存すること自体が、はたして安定したものなのかという問いをたてざるを得ない状況となった。
そうなったときの「倫理的な食とはなにか」という課題は、有機農業や動物福祉という次元の問題ではなくなったといえよう。それは、今自分が生きている土地、風土のもとで、何をどう食べることが他国に迷惑をかけずに健康で幸せに生きていけるのか、という問題なのである。日々何を食べるかは、極めて個人的な事象であるにもかからわらず、イギリスの国の形と連動する大きな課題となったのである。
2020年4月21日にG20の農業大臣がテレビ会議をおこない声明を発表した。新型コロナウイルス感染症が食料安全保障に影響を及ぼすことがないように各国が協調してフードサプライチェーンを維持するために協力することが示された。だがここで疑問がある。政治的駆け引きや投機的利益を動機としたサプライチェーンの混乱を招く行動は非難されるべきこととして、自国民に食料を優先的に確保するという動機の場合、はたして輸出制限をおこなった国を非難できるのだろうか。それはむしろ食料自給のあり方を考え、準備してこなかった輸入国の責任に帰せられる問題なのではないだろうか。
イギリスが第二次世界大戦で食料輸入ができずに大変な事態に直面した。その時はドイツのUボートが危機要因であったが、コロナウィルスがこれからのグローバル化した社会に危機要因として、影を落としている。
グローバル化した世界だからこそ、自分達は何を作り何を食べるのか。そのことを足下から考える必要があるのだろう。
(写真はすべて著者撮影。2015年)
※本サイトに掲載の文章の部分的な引用を希望される場合は、サイト名・記事タイトル・著者を明記の上でご利用ください。また引用の範囲を超える文章の転載・写真の二次利用については編集部の許諾が必要です。